【共有不動産のリスク】売却時の注意点を解説
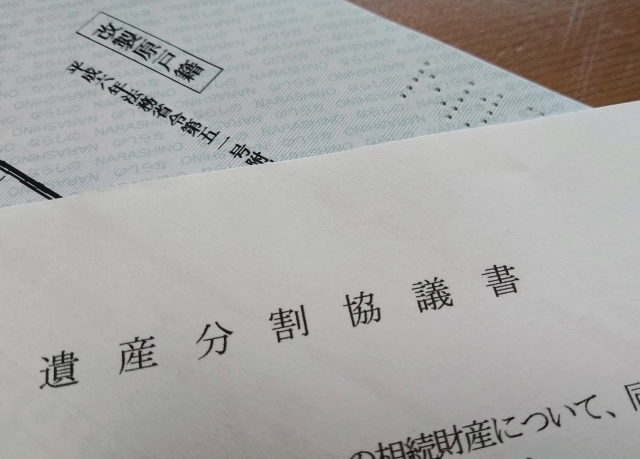
共有不動産のリスクと後悔しない売却方法を宅建士が解説します。
不動産業界に携わって40年、宅地建物取引士としてこれまで数多くの売買、相続、共有物件の調整に関わってきました。
不動産取引の中でも、特にトラブルや相談が多いのが「共有名義の不動産」です。
「親から相続した実家を兄弟で共有しているけれど、そろそろ売却したい」「昔夫婦で買った土地を分けたい」——こうしたケースには特有のリスクと難しさがあります。
この記事では、不動産の売却を検討している方に向けて、「共有不動産」が抱えるリスクや売却の際に注意すべきポイントを、専門用語をできるだけ使わずに、実務経験を踏まえてわかりやすく解説します。
そもそも「共有不動産」とは?
共有不動産とは、一つの不動産を複数人で所有している状態のことです。
このとき、それぞれの人が「持ち分」という割合で権利を持ち合います。
たとえば、3人兄弟が相続で親の土地を取得した場合、それぞれが1/3ずつの持ち分を持つような形です。
一見すると公平な形ですが、実際にはこれが大きな問題を生みます。
なぜなら、不動産は物理的に動かすことができず、また簡単に分けることもできないため、意思の違いがそのまま不動産の価値や管理に影響するからです。
共有不動産のリスクとは?
意思決定に全員の同意が必要
共有不動産を売却したり、賃貸に出したり、リフォームしたりするには、原則として共有者全員の同意が必要になります。
たとえば、以下のようなトラブルが現実に起きています。
- 長男「実家を売って現金化しよう」
- 次男「まだ使うかもしれないから売りたくない」
- 長女「もう住んでないし放置でいいんじゃない?」
このように意見が割れてしまうと、何も決められないまま、月日だけが流れていくことになります。
その間も、不動産には維持管理費がかかります。草木の手入れ、固定資産税、空き家対策費用……。
使ってもいない不動産にお金と時間が奪われるのです。
他人が共有者になる可能性がある
共有者の1人が、自分の持ち分だけを第三者に売却することは法律上可能です。
この場合、買い取った業者や他人が新たな共有者として入ってきます。
あなたにとっては「見ず知らずの人」と、同じ不動産を持ち合う状態になるわけです。
最近では、「共有持分買取業者」と呼ばれる会社が、そういった持分を安く買い取り、他の共有者に圧力をかけて全体の買収を狙うといったケースも増えています。
実家が知らない業者と共有名義になっていた――そんなご相談も実際にありました。
相続によって共有関係がさらに複雑になる
共有名義のまま年月が経つと、相続が発生し、新たな共有者が増えていきます。
たとえば
- 兄弟3人で共有していた
→ そのうち1人が亡くなり、子ども3人が相続
→ 結果として、1つの物件に6人の共有者が存在する状態に
このように、時間の経過とともに誰がどのくらいの権利を持っているのか分からなくなり、売却の話がまとまらなくなるのです。
最終的には、「山林や農地が何十人の共有者に分かれている」なんてケースもあります。
共有不動産を売却したいときの対処法
では、共有不動産を売却したいと思った場合、どのように行動すればよいのでしょうか?
ステップ① まずは共有者全員で話し合い
最も重要なのは、共有者全員が売却に同意するかどうかの確認です。
売却の意思がそろっていれば、通常の不動産売却と同じ流れで進められます。
信頼できる不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結び、買主を探す形です。
この段階で共有者同士に認識のズレがあると、後々トラブルになりますので、早めに顔を合わせて意思確認を行うことが大切です。
ステップ② どうしても合意が取れない場合
もし誰か1人でも「売却したくない」と言った場合、以下のような選択肢があります。
● 持ち分だけ売却する
自分の持ち分だけを第三者に売ることもできますが、相場より安くなりやすいことと、他の共有者との関係が悪化する可能性があるため注意が必要です。
また、買い取る側が交渉を仕掛けてくるリスクもあります。
● 裁判所に共有物分割請求をする
これは共有を強制的に解消するための法的手段です。
家庭裁判所に申し立てることで、不動産を売却し、その代金を分けることが可能になります。
ただし、時間と費用がかかるため、なるべく話し合いでの解決を優先しましょう。
共有不動産の「後悔しない売却」のために大切なこと
共有不動産の売却は、単独名義の不動産よりも遥かに複雑で手間がかかります。
それでも、「このまま放置しておけばいずれ自然と解決するだろう」という考えは非常に危険です。
私の経験上、共有不動産は、時間が経てば経つほど問題が大きくなります。
「兄弟仲が良いうちに」「親が健在なうちに」方針を固めておくことが、何よりも重要です。
専門家に相談するのが安心・確実
不動産の共有問題は、法律・税金・感情・相続といったさまざまな要素が絡み合います。
専門知識がないと、最適な判断をするのが難しい場面も多くあります。
私は40年の不動産取引経験を通じて、数多くの共有不動産問題に対応してきました。
売却の可否判断、持分整理、買い取り先の選定、調整交渉など、現場でしか分からないリアルな知恵をお伝えできます。
まとめ|共有不動産は“早めの行動”がカギ
共有不動産は、時間とともにリスクが増大する資産です。
- 売りたくても売れない
- 知らない人が共有者に
- 相続でどんどん複雑化
こうした状況を避けるためには、早めの話し合いと、専門家への相談が重要です。
もし今、共有不動産をどうするべきか悩んでいるなら、一度お気軽にご相談ください。
お悩みの整理から具体的な売却戦略まで、丁寧にお手伝いさせていただきます。
\ご相談は無料/
共有不動産のことでお困りの方は、お電話またはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせください。
059-325-7773
営業時間 9:00~18:00






